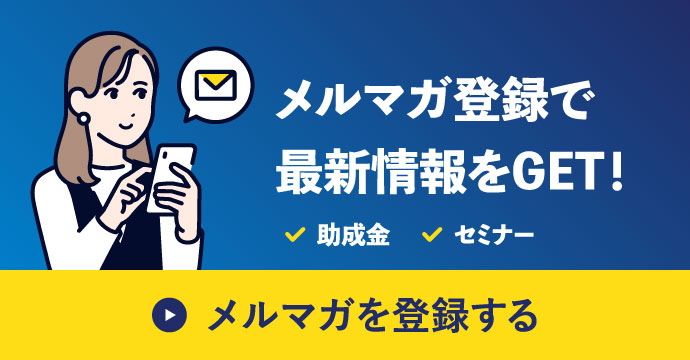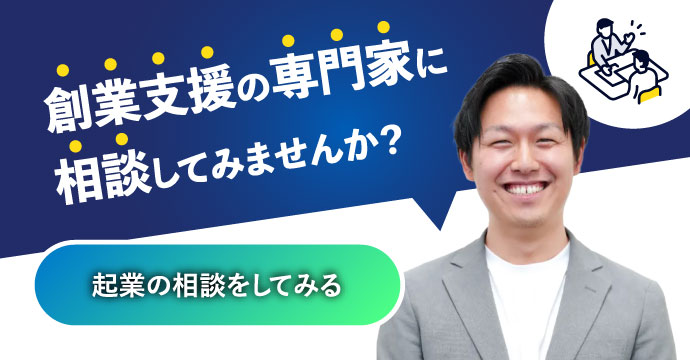はじめに
近年、社会問題を解決する「ソーシャルビジネス(社会的事業)」の存在が注目を浴びています。これは、シンプルな解決策が事業として成り立たずにいる社会課題を、寄付や募金に頼らないかたちで解決していくものです。なかでも課題が山積する地方の多くは、そういった事業を必要としています。せっかく起業するなら、自身のスキルを活かして地元に貢献したい、地域の社会課題を解決したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、地域が抱える社会課題=地域課題を解決するビジネスをはじめるには、まず課題を深く理解しなければいけません。実際に地域で暮らし、地域の人々と接することで初めて深く把握できる課題もあるでしょう。また、課題の解決を追求しながらも、利益を上げ続けるモデルを考えなければいけないという難しさもあります。
そこで今回、実際に地域課題の解決にコミットする3名に、地域課題の見つけ方や向き合い方、ビジネス化するためのポイントについて語っていただきました。仙台市、女川町、塩竈市浦戸諸島で活動されている3名の考えや体験談は、地域課題解決につながる起業や新規事業創出を志すみなさんのお役に立つ内容となるはずです!
※本記事は、みやぎ創業ガイドが主催したイベント「みやぎ地域課題ミーティング」(12月15日開催)の内容をもとにしています。
仙台市の課題解決にコミット

仙台市役所 経済局産業振興課 白川裕也さん
新しいチャレンジをする⼈(起業家)をサポートすることを仕事とする。東北に豊かな起業家の⽣態系を創ることで、東北から世界を変えるソーシャル・イノベーションを起こすことに力を注いでいる。
【地域課題の見つけ方】住民の声から見えてくる課題
仙台市の場合、市内の区役所に地域の人の困りごとが寄せられています。市では、これをもとに地域課題を把握していきます。こうして見えてきた課題に基づいて総合計画を作成したり、課として社会起業家に声をかけたり、プロジェクトの公募をかけたりしているんです。

▲「仙台市基本計画2021-2030」内で言及されている課題(イベント内で投影された資料より抜粋)
このように、住民の方々から寄せられてきた声をきっかけに可視化できる課題のほか、課題解決のために実証実験を進めていくなかで、新たな課題が見つかることもあります。
例えば現在行っている、作並・新川等を含む宮城地区西部での実証実験。隣家が遠く積雪の際には外出が危険になることから、電子回覧板を導入しようとしました。しかし、実験を進めて分かったのが「Wi-Fiがない」「携帯電話の電波を受信できていない」という状況。また、回覧板を電子化して外に出る機会が減ることで、介護が必要な人が増えるのではないか?という新たな課題も浮かんできました。
【解決策をビジネス化するときのポイント】大きな課題は細分化
地域課題をビジネス化するにあたって重要なのは、課題を細分化していくことだと思います。
人口減少・少子高齢化といった課題は大きすぎて、簡単に解決できません。目標としては「人口減少への対応」などと大きくは掲げるものの、こういった課題を細分化することが大事ではないでしょうか。緻密に細分化することで、大きな課題に繋がっている小さな課題を見つけられます。それらのうち、どの部分ならビジネス化することで対応できそうかをよく考えています。
【ビジネス化を支援する】地域と解決策を結ぶ仕組みをつくる
仙台市では、市が把握している地域課題とその解決策をもった社会起業家や企業をマッチングさせるために、公民連携窓口「クロス・センダイ・ラボ」を設けました。
仙台市には、200以上の部署と、1万人ほどの職員がいます。庁内の各部署の課題を全て把握することは難しい。加えて、課題が多い部署ほど忙しく、課題解決に向けたご提案に満足に対応できないことがあります。一元化された窓口を設置することで、民間企業等はどこに話に行けばいいのか分かりますし、関係者との調整などもよりスムーズにできるようになります。
今、仙台市が向き合っている地域課題
例えばSDGsと絡めて抽出したものでは、こちらの資料にある課題があります。介護負担の軽減、公共交通機関の縮小による交通弱者の抑制など、他地域でも見られる課題もあります。

(イベント内で投影された資料より抜粋)
このなかでも、優先順位の高いものには解決に向けた開発費を出す、実証実験への補助金を用意する、といった仕組みをつくろうとしています。課題解決にチャレンジする方を惹きつけると共に、解決へのスピードを上げていきたいと考えています。
女川町の課題解決にコミット

特定非営利活動法人アスヘノキボウ 後藤大輝さん
女川町の社会課題解決を通じて、日本・世界の社会課題解決に貢献することをミッションとする団体・アスヘノキボウで、女川町の活動人口(女川町民に限定せず、女川町と関わり、女川町をフィールドとして活用する人口)の創出に取り組んでいる。
【地域課題の見つけ方】リサーチをもとに課題を整理
アスヘノキボウの場合、震災直後はデータを使って、最近は住民の声を直接聞いて、課題を可視化しています。
震災後は、ハリケーンによる被災から復興したアメリカの都市・ニューオーリンズを参考にしたデータ事業を行いました。街の9割が水没したニューオーリンズが、災害から立ち上がり起業家が集まる地域となったことを知り、なぜこの街はそこまで復興できたのかをリサーチしました。その際、データブックが活躍したことを知ったんです。
このデータブックと一般的な統計データとの違いは、調査員が街に繰り出し、住民にインタビューをした点です。住民への地道な聞き取りから分かった課題感や不安を指標化していました。そのデータをもとに、住民が話したことはそもそも課題なのか、課題ならばどれくらい深刻なのか考える場を設け、課題解決に向けたプロジェクトを生んでいく。このニューオーリンズの事例を参考に、女川でもデータ事業を通じ、課題を可視化していきました。
リサーチをもとに地域課題を可視化していくと、大きな課題だと思っていたものが、実際はそこまでの問題ではないことが分かった、なんてこともありました。
例えば、鹿の獣害問題。確かに農作物被害は出ていて、農家の方にとっては解決しなければいけない課題です。同じように森林被害が語られることも多くありますが、少なくとも女川では、鹿による山林への影響はあまりないことが研究で分かってきました。町民が、あれは鹿がやっていると思ったものが、よくよく調べると他の要素が主な原因だということもありました。しっかりと調査することによって、課題への適切な理解が進んでいるように思います。
【解決策をビジネス化するときのポイント】関係性を丁寧に築く
地域課題の解決は、長期戦になることが考えられます。そもそも、なかなか解決しないから課題になっている背景もありますので。
長期戦になるからこそ、どこを目指すのか、どんなアプローチで取り組むのか、といったことに加えて、チームの体制や関係者との繋がりも重要になってくると思います。アスヘノキボウが用意している「お試し移住」制度を使い、課題の当事者である地域の方との関係性を築く時間をつくることもおすすめです。
今、女川町が向き合っている地域課題
「地域課題」という言い方はしていませんが、女川のビジョンを実現するための取組候補をみれば、どういった分野に課題を感じているか分かるかと思います。

(「女川未来ビジョン2021」より抜粋)
これらは、町の公民連携室、経営者さん、銀行の支店長などのキーパーソンの方々が集まり、女川町の未来をどんなものにしたいかディスカッションを重ね、その実現に向けて必要なプロジェクトをまとめたものです。
他にも、遊休・未利用不動産の利活用、スポーツを通じた健康プロジェクトなど、多くの具体的なアイデアを提言しています。
塩竈市浦戸諸島の課題解決にコミット

株式会社MAKOTO WILL 門馬麻美さん
株式会社MAKOTO WILLが総合的なマネジメントを行う、塩竈市浦戸諸島の活性化を目指す「浦戸再生プロジェクト」で、プロジェクトマネジメントを担当。自身も浦戸諸島にルーツを持つ。
【地域課題の見つけ方】足を使って課題を可視化
浦戸諸島では現在、キーパーソンへのヒアリング、島民同士のディスカッション、島民へのアンケートの3つを行い、この地域の課題を見極めています。
まずはじめにキーパーソンへのヒアリングを行うのは、本質的な課題の抽出につなげるためです。「この人に聞かないと物事が動かない」といったキーパーソンを、市の方と連携して探します。その後、ヒアリングから分かった課題の当事者・関係者となる島民を招き、島民同士のディスカッションを行い、これらの結果からたてた仮説をもとに、アンケートを実施しています。

(浦戸諸島でのディスカッションの様子)
こうしたプロセスを経てみて、意外にもこの課題の優先順位は低いんだな、という発見もありました。
「離島」と聞くと、買い物の不便さが大きな課題かと思いがちです。しかし、島民からは、アクセスの向上はあまり求められていないことが分かりました。皆さん幼い頃から船を使い本土へ渡って買い物をしているため、そもそも不便だと感じていない。また、この船を使っての移動を、一種のエンターテイメント、息抜きとして楽しんでいるんです。逆に便利になってしまい船で本土へ渡る機会が減るのは嫌だ、という意見もあり、自分たちの想定と違う現実が見えました。
【解決策をビジネス化するときのポイント】その課題の解決にニーズはあるのか精査
このように、アンケートや対話を通じて、解決するべき課題なのかを明らかにすることは、地域課題と向き合うにあたって大事なことだと思います。
『未来を実装する』という馬田隆明教授の著書の中で、本質的に必要なことは、理想の状況と現在の状況を照らし合わせて、そのギャップを埋めることだという話が出てきます。この考え方がとても大事だと思うんです。地域住民の理想に対して、現状足りないものは何なのか、を考えること。「地域住民の理想に対して」という部分からぶれてしまうと、課題を解決したところで、それはよかったのか?となってしまいます。解決ニーズを見極めることが重要なのではないでしょうか。
また、ビジネス化して解決を目指すわけですから、誰がお金を払うのかを考えなければいけません。
浦戸諸島の場合、島民は300人ほどしかいません。どうにかして外貨を稼がなければ、課題を解決するお金はありません。その解決策にお金を払ってくれる人がいるのか?それは誰なのか?現在試行錯誤しているところですが、これらの疑問に対する答えをしっかりと考えないといけません。
今、浦戸諸島が向き合っている地域課題
ヒアリングの結果「島単体で存続していくことは経済的に厳しい」という認識を島民が共有していることが分かりました。そこで、先ほども少し出てきましたが、外とのつながりはもちろん、浦戸諸島内の4島5地区のつながりも必要だということが見えてきました。
細かく課題を分析していくと、特に解決ニーズが集中しているのは「住まいがない」「産業がない」という2つの課題でした。これらの解決に向けて、空き家活用や一次産業の活性化から動こうとしているところです。
おわりに
本記事で紹介された事例や課題が、地域に貢献したいという想いをビジネスで実現したり、ソリューションをもっている企業が地方に進出したりするきっかけとなればと思います。
今回話していただいた3名からもっと詳しいお話を伺いたいといった要望がございましたら、みやぎ創業ガイドまでご連絡ください。マッチングの手助けをさせていただきます。