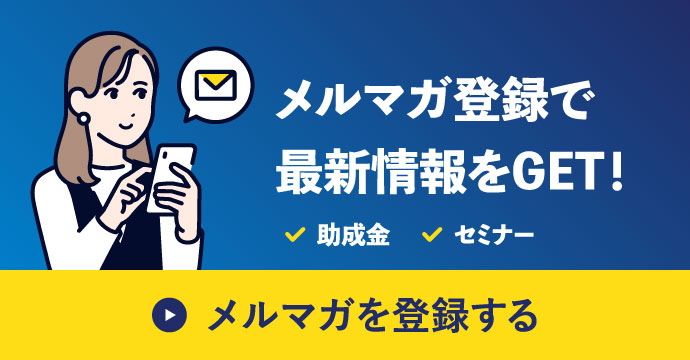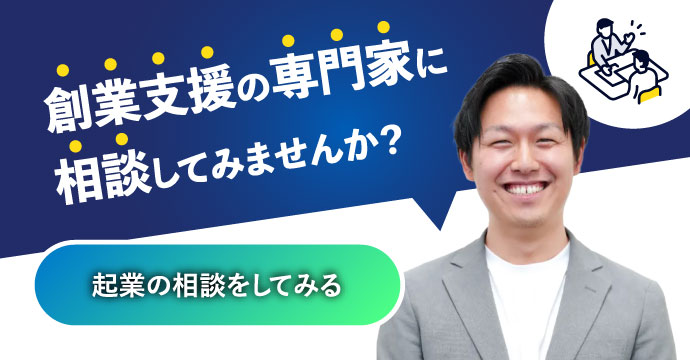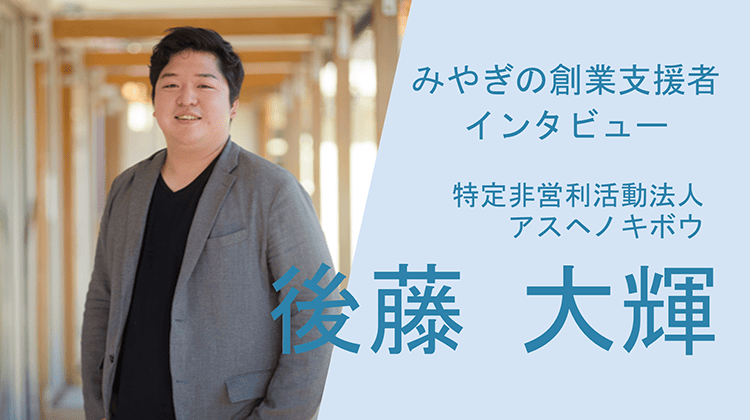「起業について相談したいと思っても、どんな人が聞いてくれるのだろうか…」と不安に思ったことはありませんか?そんな不安を少しでも和らげようと、「みやぎの創業支援者インタビュー」では、宮城県各地で起業家の支援を行う方々の人物像を明らかにしていきます!
第4回目となる今回は、女川町で起業・創業支援を行う特定非営利活動法人アスヘノキボウの後藤大輝さん。支援プログラムや女川町の特徴などを語っていただきました。
自己紹介をお願いします。
特定非営利活動法人アスヘノキボウの職員として、2016年10月より働いております。もともとは東京出身で幼稚園から大学までずっと東京で過ごしていましたが、震災ボランティアで東北とは縁ができました。その後HLABというサマースクールで女川町に訪れ、現在私が主催する「創業本気プログラム」の1期生として参加。当時は大学3年生で進路に迷っていましたが、活き活きとした大人たちと出会う中で「東北なら自分が社会に大きな影響力を与えられるかもしれない」と感じました。
それから今のアスヘノキボウ代表理事の小松洋介と出会い、女川で世界の復興の知恵と人材のネットワーク事業を考えているという話を聞き「それ私やりたいです」と、入社を決めました。現在6年目を迎えております。

後藤 大輝
2011年3月11日の東日本大震災後を機に、大学在学中に女川町(東北・宮城)へ移住、2016年10月にアスヘノキボウ入社。女川町の活動人口(女川町民に限定せず、女川町と関わり、女川町をフィールドとして活用する人口)の創出に取り組んでいる。他には女川町の社会課題をテーマにした企業研修、さとのば大学 女川事務局等のコーディネーターを務める。2020年8月に「(屋号)オナガワーシカ」を個人事業主として開業し、新たな地域の資源としての「鹿」の流通に取り組んでいる。有志団体である三陸リアス式ジビエ協同組合に所属し、食肉処理施設(女川町)の運営にも関わる。第二期女川町復興連絡協議会(FRK2) 事務局。2017年3月 明治大学国際日本学部 卒業。
アスヘノキボウの起業支援の内容と特徴を教えてください。
私たちは「創業本気プログラム」というプログラムで創業支援を行っています。1〜2年以内に地方で起業する意思がある方を対象としており、基本的には、土日2日間×3回の6回行われる女川町での講義に出ていただく通学制。ビジネスアイデアからビジネスモデルを練り、それぞれのビジネスプラン形成までを伴走支援します。
特徴としては3つあって、1つ目は、女川町以外で起業したい方も対象者としてみなしていること。たとえば他の自治体では、自分の地域で起業する方だけをサポートするなど、制限があることも少なくないと思います。ただ、我々のプログラムは「女川町以外の地方で起業したい方」も受講が可能。むしろ女川で学ぶことで町と縁ができて、たとえ別の場所でビジネスを始めたとしても、その後も女川の活動人口になる可能性があると考えています。
2つ目は、1回あたりの参加者が3〜4人という少人数制であること。参加者1人に対してメンターが1人つくマンツーマン制で、起業に対しての本気度が非常に高いコミュニティです。2021年度下半期で10回目を迎え、卒業生が42名のうち26名が起業しています。少人数で密にサポートしていくことが効果的だという考えています。
そして3つ目が、地方での起業の仕方を学びとして提供していること。都市部と比べた時の地方での起業は、大きく分けて「関係者との距離感」に違いがあります。地方自治体は、まちで活躍する企業や個人などと非常に密接な関係性を築いていることが多いため、起業する上ではその人たちをどのように戦略的に巻き込んでいくかがポイントです。また、地方特有の利権関係や役場の動かし方なども重要であるため、地方に特化した起業の学びを提供している点だと思います。

起業支援する上で大切にしていることは何でしょうか。
端的に言うと「人に寄り添うこと」です。創業本気プログラムだけでなく、例えばアスヘノキボウにインターンで来てくれる学生に対しても、その人がどんな背景を持ってなぜ女川に来てくれて、どんなことに挑戦したいと思っているのか。あるいは、どんな不安を抱えているのかなどを、とにかく考え抜きます。私たち中間団体が個人としっかり向き合い、その方の目的や性格に合わせたコーディネートを把握・提供できていることは強みだと思いますね。特に、起業するに当たっては、「なぜあなたがその事業で起業するのか?」が最も大事な点だと考えており、徹底的に起業家と向き合います。多くの起業家の方の話を聞くと、起業は良い時だけではなく、主に人材やお金の部分で3年以内に苦しいタイミングが必ずきています。事業を絶えず進ませる軸となる志や想いが大切で、それが困難を乗り越える支えになると信じています。
また、僕自身も女川に来てからいろんな復興の話や経営者のエピソードを聞いて、ちゃんと自分の想いを理解し言語化できることが重要だと感じています。今の時代は外部環境の変化がかなり激しいため、市場に合わせて求められやすいものを創るというよりかは、どんな状況でも変わらない軸を重要視しています。深い想いを持った方こそが、ビジネスを長く継続できているように感じるのです。
創業支援に関する女川町の特徴を教えてください。
女川町の特徴は、まず経営者、自営業の方が多いことです。人口に対する自営業の割合が非常に高く、すなわち自らがオーナーとしてビジネスに取り組んでいる方が多くいます。前述の創業本気プログラムの最後には「最終発表会」という、町長や町の経営者を前に自らのビジネスプランをプレゼンする場も設けていて、より多くの人と繋がる機会を提供しています。
また、そのコミュニティの強さも特徴の一つで、背景にあるのが女川町の「コンパクトシティ」というブランドデザイン。つまり女川駅前に飲食店や制作販売をする工房、あるいはコワーキングスペースなど、自然と人が集まる設計がされていて、活発なコミュニケーションが生まれています。ふらっと飲みに行くと、それこそ町長や経営者の方と居合わせたり話ができたりして。経営者はどうしても孤独になることが多いと思いますが、そんな経営者同士のコミュニティが日常に根付いていることは、女川の強みなのではないかと思います。
あとは、震災を経験していることも特徴です。東日本大地震で、女川は町の7割が津波の被害を受けました。それでも、またここで事業を立ち上げている方がいます。そんな方々は「なぜ自分が再び女川でビジネスをやるのか」や「誰のためにサービスを提供するのか」などを、とことん突き詰めている印象があります。もちろん生活のためという側面もあるとは思いますが、それとはまた別の、強い使命感や情熱を持っている経営者が多いのではないかと思っています。
これからの課題、そして今後取り組んでいきたいことは何ですか。
これから取り組んでいきたいのは、地域課題起点での起業をする人のサポートです。これまでの創業本気プログラムは、基本的に参加者個人の想いからビジネスを創っていました。ただ、震災から10年が経過して、女川町が“復興”から“地域づくり”というフェーズに変化しています。すると、徐々に山間地域や水産資源にまつわる、いわゆる社会課題が生じてきており、それに対して使命感を持って解決する人材を増やしていきたいのです。
現段階で具体的な方法は決まっていませんが、「〇〇の分野で創業したい人を応援します」というように、応募型で進めることを想定しています。また、社会課題へ挑むとなると、町の関係者やステークホルダーとの関係性もより重要になります。そこで、多様な方々とのディスカッションの場や、あるいは地域課題を深く理解するためのコンテンツを設けることで、これまでとは違ったプログラムにできればと考えています。

女川町での起業を考えている方へメッセージをお願いします。
私は、地方でビジネスを行うなら、女川以上に起業家の密度や想いが強いコミュニティはないと思っています。これから女川はもちろん、女川以外で起業を考えている方も大歓迎です。ぜひ私たちのコミュニティに参加していただいて、女川から日本や世界を良くしたいという想いの方々に出会えることを望んでいますので、ぜひ女川に来ていただけたらと思います。
関連記事
▶【大崎市で創業支援】みやぎの創業支援者インタビュー|株式会社スリーデイズ・伊藤 理恵
▶【南三陸町で創業支援】みやぎの創業支援者インタビュー|株式会社ESCCA・山内 亮太
▶【丸森町で創業支援】みやぎの創業支援者インタビュー|丸森CULASTA・島 征史